ざっくりと言えば、東大合格者の歴史は4つほどの時期に分かれる。まず戦後直後の1949年から1968年までの約20年。この時期は圧倒的に日比谷を中心とする都立高校が強く、他でも湘南や県立千葉・浦和などが強く、あまり地方色がない。この頃の東大は関東の地方校といった様相がある。本書によれば一応この頃が最も多様性に富んでいたそうだが、それは1〜2人合格校が多く統計上そういう結果が出ていただけであって、合格者上位100校を見るとすでに寡占が始まっていたことがわかる。この頃の日比谷や西高校の合格者は100人を超え、今の開成や灘と何ら変わらない。私立や国立はそれほど強くない。
この状況が次第に変わり始めるのが60年代後半〜70年代前半にかけてである。69年度入試が東大闘争で中止になったように、公立高校の多くは学生闘争に巻き込まれた。加えて、都立高校で悪名高き学校群制度が始まったのを皮切りに全国でこれが導入され、公立高校の大失墜が始まる。学校群制度や小学区制度とは反エリート主義者の誤解によって生じたものだ。確かに一つの高校に多種多様な知性を持った人間が集まるようになったかもしれないが、それは多様性の上昇という結果をもたらしたわけではない。所詮人間の多様性など偏差値で区切った程度で減少するものではなく、結局彼らは人間というものを信用できなかったのだ。
学校群制度・小学区制度は公立の名門校を破壊して「貧乏人でも東大に入れる」という公教育の理念をつぶし、私立高校を育てるという目的とはある種正反対の結果を生んだ。68年に早くも灘が1位をとると、以後公立高校がこの座を奪還することは現在に至るまで一度も無い(国立を含めれば71年に筑附が、73年に筑駒が1位を獲得)。さらに言えば、1位に話を限るならば82年以降2010年現在にいたるまで、開成が1位を譲ったことがない。
70年代はまだしも、80年代前半は公立暗黒時代であった。この時期にあって意地を見せていたのは、やはり関東圏であった。80年代の場合、都立のうち西・戸山の2校、そして湘南・千葉・浦和の3校でほとんど20位以内の公立高校は終わってしまう。都立に話を絞れば、60年代最強を誇った日比谷は早々に脱落。校風が自由であった伝統に低い成績層が混ざったという悪影響。逆に、西と戸山が生き残ったのはスパルタ式の教育方針による。しかし、その西と戸山もじりじりと下がり、77年を最後にトップ10から消える。
第三の時期は80年代後半〜90年代前半である。87年に東大・京大のダブル受験が可能になった。第二期の影響で本当に頭の良い生徒は私立・国立に行って東大入試も楽々合格し、公立に行った生徒は最低点ギリギリを狙うという風潮が生まれた。この風潮は現在までもなんら変わっていないわけだが、この風潮の中でダブル受験を認めればどうなるだろうか。すなわち、関西の有力な高校が一気に東大に流れ込み、地方公立の「合格最低点狙い」東大受験生は、さらに押し出されることになった。これほどの公教育つぶしも無い。87年の開始年ですでにトップ20に公立は湘南・千葉・浦和しかいない。翌88年には湘南が沈み、89年には制度が元に戻って東大専願になったにもかかわらず、この流れは変わらず、やはり千葉と浦和のみがトップ20に顔を見せた。最も割りを食ったのは都立高校で、80年代後半にはトップ20から完全に姿を消した。90年代前半が最もひどく、トップ100に至るまでずらっと私立が並ぶ。ランキングの半分は私立である。
そして第四の時期が90年代後半〜2010年の現在までである。特徴としては、地方も含めた公立高校の巻き返しである。これは時代の流れであった。日教組加入率が下がり、また私立偏重の難関大学合格は悪しき反知性主義の結果であるという自己批判に、公立高校側がようやく至ったのである。一斉に学校群・小学区制度が廃止になり、大学区制度や県内一学区体制がとられるようになる。この間に公教育の失ったものはあまりにも多かった。この頃から10〜20人の合格者をコンスタントに出す「県内トップ校」の顔ぶれが登場、もしくは復活し始める。日比谷でさえ見事な復活成長を描き始めた。これは二つの意味を持つ。すなわち、トップ30の私立の牙城はついに崩せない状態となり固定化した。2005年度など、20位までに1校もなく、22位に岡崎、23位に、浦和、24位に土浦第一と3校あるのみである。ちなみに、私の入学年である04年も、トップ30に入った公立高校は岡崎、土浦第一、旭丘、一宮の4校のみであった。我が母校も含めて、なぜか愛知県の強かった年でもあった。その一方で、私立が強いまま公立高校にもエリート主義が復活したため、公立高校同士でも二極化が進み、東大合格のさらなる寡占化が進んだということだ。さて、第四の時期はいつまで続くであろうか。なお、60年間トップ10から漏れなかった高校が一つだけある。麻布高校である。
この他、県ごとのデータや60年分の累積データ。女子校や男子校、宗教系といった区切りではどういった結果が出ているかという分析が掲載されている。データ中毒にはたまらない一冊となっている。ただし、一つだけ言わせて欲しい。校正はもっとしっかりやろう。本文中には誤字脱字が見当たらないものの、データ部分がひどい。量があまりにも多かったので苦労のほどは理解できるが、多分あまり校正を通していない。記号の抜け、インデントのズレ、表記の揺らぎが当たり前のように存在し、普通に読む分には問題ないが精読しようとするとちょっと辛い。あと、誰か早く京大版・慶応版・早稲田版・阪大版・名大版を執筆するべき。無論、この著者でもかまわないので。
 東大合格高校盛衰史 60年間のランキングを分析する (光文社新書)
東大合格高校盛衰史 60年間のランキングを分析する (光文社新書)著者:小林哲夫
販売元:光文社
発売日:2009-09-17
おすすめ度:
クチコミを見る

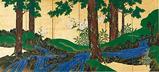
 損保ジャパン美術館のユトリロ展を見に行ってきた。ユトリロは20世紀前半に活躍したフランスの画家で、都市景観画で活躍した。
損保ジャパン美術館のユトリロ展を見に行ってきた。ユトリロは20世紀前半に活躍したフランスの画家で、都市景観画で活躍した。


